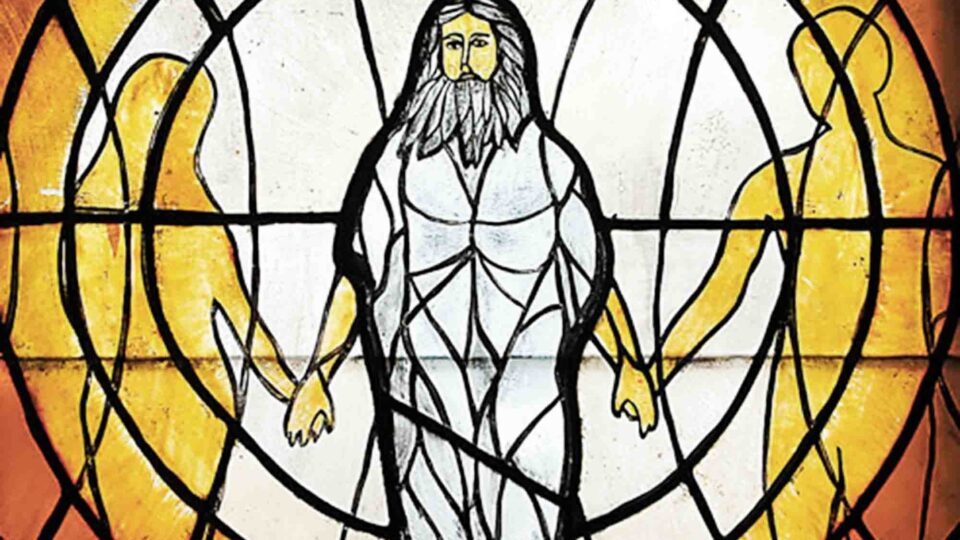あゆみ 2024年11月
バリー・ケンズ神父
私は16年前に専門学校の講師をしました。担当はケアワーカーの資格を目指す30名のクラスで 1回 2時間 10回の授業をしました。
その人たちは資格をとって介護施設障害者施設、病院などで働くことになります。その施設、病院には教会系のものもあり、また患者さん、入所者さんにはクリスチャンもいます。そこで私はキリスト教という学科を受け持ちました。
そのクラス30名のうち20名の女子、若い茶髪の子もたくさんいました。そして10名の男子の中にはグリーンに染めた髪を立ち上げさせている子もいました。夏休みを終えた9月から始まる学科だったので そのような風貌の子が多かったのだと思います。みんな20代~30代の若い生徒でした。
私は自己紹介の「皆さんの中にキリスト教と関係があった人はいますか?」と質問しました。すると一人の生徒が教会の幼稚園に通っていたと、もう一人の生徒は団地の中にキリスト教信者のおじさんがいましたと答えてくれました。たった2人だけでした。
私は最初の授業でキリスト教というよりキリスト自身のことの方が中心ですと話しました。
そして教科書として『新約聖書』と遠藤周作さんの『イエスの生涯』その2つを使いました。
私は授業の中で「共感」という言葉を度々使いました。なぜなら生徒さんたちが卒業して実際に働いたときにそこで患者さんや入所者さんと共に感じる「共感」が大事だと思ったからです。

では、イエスの生涯について
『ナインの未亡人』の面、イエスは一人息子を亡くして泣き伏せているその母親の涙を見て共に感じました。そして彼女の息子を生き返らせました。
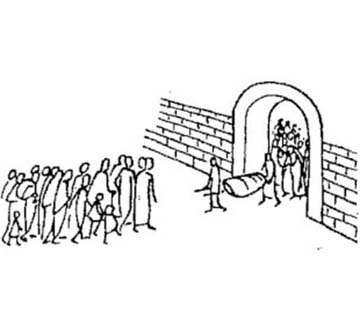
『10人のらい病人』の場面、イエスは10人のらい病人の淋しさを共に感じました。
そしてその10人たちをきよめられた。しかし神に感謝したのは一人だけ、でも恩知らずの9人を罰することはなかった。

『山上の説教』の場面、義に飢え渇いた群衆と共に感じました。そして「義に飢え渇くものは幸いである」と群衆にお話になりました。
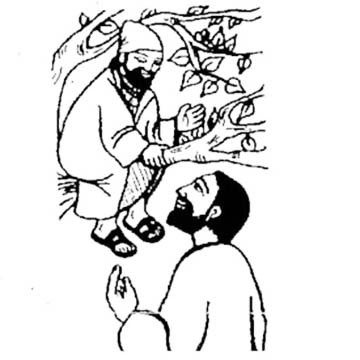
『徴税人ザアカイ』の場面、彼はお金持ちではあったが町の人たちに嫌われていました、なのでイエスに大きな憧れをもっていました。イエスはザアカイの孤独を共に感じました。そしてザアカイの家に泊まり一緒に食事をしました。
『出血の止まらない女』の場面、彼女は長い間何をしても出血が止まらない病でした。イエスは彼女の恥ずかしさを共に感じました。そして出血が止まると彼女の信仰が病を治したのだとおっしゃいました。
『姦通の女』の場面、姦淫の罪を犯した女が石打の刑にされようとしているのを裁くことなく彼女の可哀そうな状態を共に感じました。そして彼女は誰にも惹かれることがなかった。
『エリコの盲人』の場面、エリコという町で一人の盲人が「イエスよ、私を憐れんでください!」と叫んでいました。イエスはその男の声を聴き共に感じました。そして彼に光をお与えになりました。

イエスの教えとして新約聖書の『放蕩息子のたとえ話』『善きサマリア人のたとえ話』を研究しました。
中でも『善きサマリア人』では道端に倒れている血だらけの人をひとりの祭可、1人のレビ人は見て見ぬふりをして通り過ぎて行ったが、一人のサマリア人が彼を気の毒に思い丁寧に介護しました。
これは共感の例です。『共感』はケアワーカーにとってとても大事なことだと思います。
そのクラスで意見を出し合って平和の祈りを考えました。
自己中心はケアワーカーにとって妨げだと思います、けれどその祈りの中で私に助け導きをお与えくださいと祈ります。
自分の力だけでこの共感を実行することはできないと思います。
人間的な力以上のものが必要だと思います。
優しい神様はその助けと導きを喜んで与えてくださいます。頼みましょう!
この精神は「AA ( アルコホリック・アノニマス ) 」12のステップの中にあります。
依存症の人たちが自分の弱さを認めて「ハイパワー(自分の力を超えた自分より偉大だと認められる力」の配慮の下に置く決心をする。